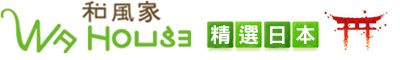現在跟以前一樣(変わりはありません,かわりはありません),只要到夏天就熱到不行。但以前是連冷氣(クーラー)與電風扇(扇風機,せんぷうき)的時代,一定是以前的人熱到不行(昔の暑さのほうが堪らなかったはず,むかしのあつさのほうがたまらなかった)。
但據說奈良時代及平安時代的人在夏天就能享受(楽しんでいた)到刨冰(かき氷,かきごおり)及在飲料裏加冰塊(on the rocks,オンザロック)的樂趣。但在沒有冰箱的時代,要怎樣才能拿到冰塊(いったいどうやって氷が手に入った,いったいどうやってこおりがてにいった)?

『日本書紀(にほんしょき)』裏記錄挖一丈多土(土を掘る,つちをはる),拿草蓋在上面,鋪廬葦(茅荻を敷く,かやすすきをしく),將冰取出,放在上面(仁德天皇紀)及冰室的構造(氷室の構造,ひむろのこうぞう)。
說到仁德天皇,是奈良時代之前的古墳時代(こふんじだい)的人物。雖然以前庶民階層可能吃不到冰(口には入らなかった,くちにははいらなかった),但當時貴族階層早就在吃冰了。這種冰是在冬天儲存的天然水,在夏天最熱時使用(夏の盛りに利用する,なつのもりにりようする)。
由於在正倉院(しょうそういん)的文獻當中,曾有買冰的記錄,到了奈良時代,就已經出現仲夏賣冬天做好冰(冬に仕込んだ氷を真夏に売る,ふゆにしこんだこおりをまなつにうる)的冰店(氷屋さん,こおりやさん)。
仲夏,宮中的菜單(献立,こんだて)裏,一定有稱為削冰(削り氷,けずりひ)的刨冰。冰室建造於京城(畿内,きない)各地,在冰室的附近所挖掘出的水池數目達到540個,稱為「延喜式」。
這些冰是在淋上甜醬(甘葛をかける,アマズラをかける)後就成為的現代風的刨冰及將冰浸泡在酒裏使用(酒に浸して用う,さけにひたしてもちう),類似現在將冰加在飲料內的作法。平安時代的女性作家(女流作家,じょりゅうさっか)清少納言(せいしょうなごん)的『枕草子(まくらのそうし)』及紫式部(むらさきしきぶ)的『源氏物語(げんじものがたり)』當中都有寫到刨冰,可見她們兩位都是刨冰的愛好者。